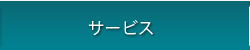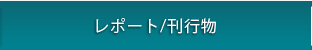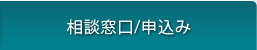サービス
財務書類の公表まで及び、公表後に取り組むべきこと
平成21年6月に総務省に設置された「地方公会計の整備促進に関するワーキンググループ」において「新地方公会計モデルにおける連結財務書類作成実務手引【総務省方式改訂モデル編】」が取りまとめられ、公会計対応待ったなしとなりました。
財務書類の公表までに取り組まなければならないこと、また、財務書類の公表後に取り組んでいただきたいことについて、固定資産の関係を中心に以下まとめました。
【公会計スケジュールと作業イメージ】
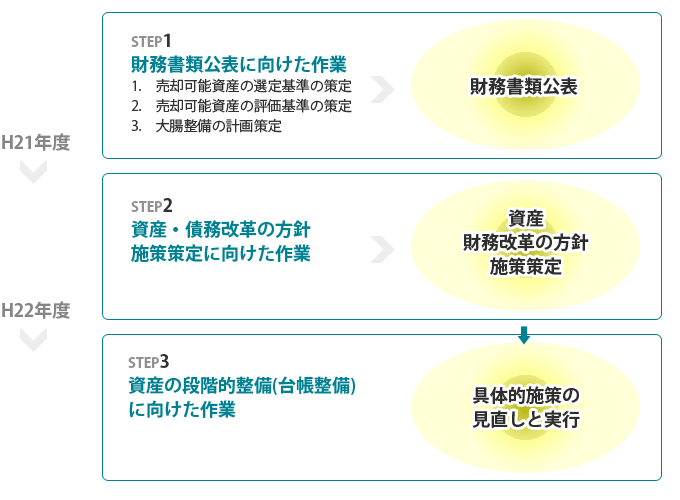
STEP1 財務書類の公表に向けた作業
財務書類の公表までに最低限、取り組まなければならない事項は下記3点です。
(1)(2)は、貸借対照表注記事項として定められていることに加え、実質的にも、かんぽの宿問題でも代表されるように、資産の売却や有効活用に至る手続の適正さを確保するために重要です。
(3)については、総務省方式改訂モデルを採用する場合、初年度の台帳整備は行わずとも財務書類の作成は可能ですが、資産台帳の段階的整備が求められていることから、開始時財務書類の作成までに計画の策定は必要です。
STEP2 資産・債務改革の方針・施策策定に向けた作業
財務書類の公表後、年度末までに、いわゆる「地方行革新指針」において、財務書類の作成・活用等を通じて資産・債務に関する情報開示と適正管理を一層進めるとともに、国の資産・改革も参考にしつつ、未利用財産の売却促進や資産の有効活用等を内容とする資産・債務改革の方向性と具体的な施策を策定することが要請されています。
検討対象とされている売却可能資産に係る事項を検討することはもちろんですが、そのほかにも、ストック情報の整備など、新地方公会計モデル導入の目的や効果等を踏まえ、地方公共団体において、方向性や具体的施策を策定する必要があります。
STEP3 資産の段階的整備に向けた作業
総務省方式改訂モデルを採用している場合、資産台帳の段階的整備を実施していく必要があります。資産台帳の整備は、新地方公会計モデルの大きな目的の一つとされており、現物との照合を含めた精緻な台帳整備が求められています。
また、純粋に公会計対応として求められる台帳の項目は、資産の種類や評価額、財源といった、あくまでも会計上、必要とされる項目のみですが、せっかく全庁的に棚卸の調査を行うのであれば、この機会に、修繕等の履歴管理や有効活用に資する情報の整備、また、土壌汚染や耐震診断等の各部署で実施している調査等の項目についてあわせて整備することも有用です。